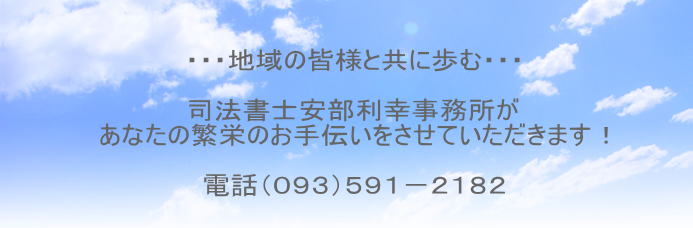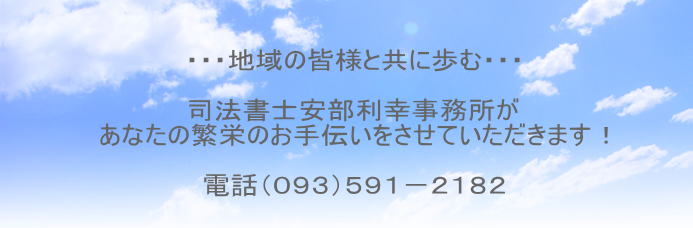もし手形や小切手を紛失したら・・・
1、手形・小切手の振出人に急いで連絡して下さい。金融機関に対して振出した手形・小切手の紛失届をするよう、お願いして下さい。拾得者が勝手に手形交換に回した場合に支払いを停止するためです。
2、警察に遺失届を出してください。そして遺失届受理証明書を発行してもらって下さい。裁判所に提出する書類となります。
3、振出人に手形・小切手の振出証明書の作成をお願いして下さい。裁判所に提出する書類となります。
4、紛失者が簡易裁判所に公示催告の申し立てをします(予納金と切手が若干必要)。司法書士はこの書類の作成・提出代行ができます(有料)。
5、紛失者は公示催告期間(6ヶ月)経過後公示催告期日に裁判所に出頭して下さい。本人が出頭できないときは、代理人許可の申し立てが必要です。
6、除権判決が確定すれば紛失した手形・小切手は無効になります。
重要・紛失した株券の再発行制度が変わりました!
有価証券のうち株券についてのみ、公示催告・除権判決制度が平成15年4月1日より廃止されました。(他の有価証券、手形、小切手については廃止されていません)
新制度では、会社に株券喪失登録簿の備置を義務付けられました。
(1)株券を喪失した者が会社に株券喪失登録の申請を行います(その際に火事で焼失した場合には焼失届証明書、盗難に遭った場合には盗難証明書を添付)。
株券喪失登録された株券を所持している人は、株主名簿の名義人であれば会社からの通知により、名義人でなければ名義書換の申し出の際に株券喪失登録がされていることがわかりますから、株券喪失登録が虚偽であると主張する場合には、登録異議の申請をすることができます。ただし、これは登録期間内(株券喪失登録後1年間)でなければなりません。
この異議の申請がされれば、会社は申請後2週間を経過した日に株券喪失登録を抹消します。
(2)1年間の登録期間の満了日に株券は無効となり、会社は株主名簿に株券無効の記載をします。
(3)株券無効となる日をもって、株券を喪失した人が株主名簿の名義人でなければその人に名義書換がなされたものとみなされます(株主名簿の名義人であればそのままです)。
ただし、株券が無効になった後にその株券の譲渡を受けた者はいかなる場合でも保護されない(善意無重大過失によって株券を取得しても権利者になれない)という問題は従来と変わらないので、株券喪失登録について申請者と株券の所持人に争いが生じた場合、最終的には裁判所で解決がはかられることになりますが、株券が別の第三者に移転して新たな権利者が生じることを防止するために上記2週間の間に裁判所から株券を譲渡してはならないという処分禁止の仮処分命令をしてもらわなければならいことになります。
よって、株券を譲り受ける場合には、株券喪失登録がなされていないかどうかを会社に確認することが唯一の自衛手段であると言えます。
また、制度の変更に伴い、株券を発行する規定のある株式会社の定款で株券の再発行に関する規定について、変更が必要になります。以下に制度変更後の参考文例を掲げます。
(株券の再発行)
第10条 株式の分割・併合、株券の毀損又は汚損等の事由により株券の再発行
を請求するには、当会社所定の書式による請求書に、請求者が署名又は
記名押印し、これにその株券を添えて提出しなければならない。
② 株券喪失登録の申請をする者は、当会社所定の書式による申請書に、
申請者が署名又は記名押印し、これに次の資料を添えて提出しなければ
ならない。
(1) 株券の取得の事実及びその株券の喪失の事実を証する資料
(2) 法務省令に定める資料
③ 株券失効手続により無効となった株券の再交付を請求するには、株券
喪失登録者が、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印して
提出しなければならない。
↓↓↓ 旧規定(平成15年3月31日まで)↓↓↓
(株券の再発行)
第10条 株券の再発行を請求するには、当会社所定の請求書に記名押印し、
これに株券を添えて提出しなければならない。ただし、株券を喪失
したときは、除権判決の正本又は謄本を添えて提出しなければなら
ない。
|